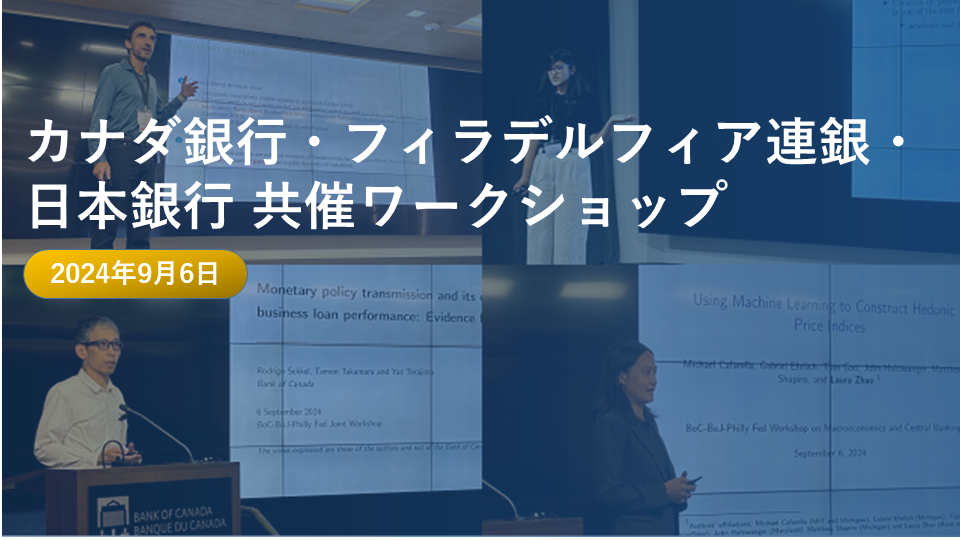前のページへ
金研ニュースレター:2025年カナダ銀行・フィラデルフィア連銀・日本銀行共催ワークショップ

カナダ銀行、日本銀行、およびフィラデルフィア連邦準備銀行は、2025年11月14日に日本銀行本店においてワークショップを共同で開催しました。
このワークショップは、カナダ銀行と日本銀行との間で2013年に開始され、2019年からはフィラデルフィア連銀も主催者として参加しています。目的は、中央銀行と学者における研究の議論を促進し、政策に関連する最新の研究を共有することです。今年の第8回ワークショップでは、学界より、Markus Brunnermeier氏(プリンストン大学)と藤原一平氏(慶應義塾大学/東京大学)の2名の発表者を招待しました。
本ニュースレターでは、ワークショップで発表された論文の中から、金融政策と、失業率や実質為替レートなどのマクロ経済変数に関する本源的な課題に取り組む4本の論文を要約しています。
1. 住宅ローン金利リスクとショックの波及

住宅ローン市場の構造は国によって異なります。カナダ、英国、日本では、変動金利型住宅ローンが主流である一方、米国、デンマーク、フランスでは固定金利型住宅ローンがより一般的です。こうした構造的差異が持つマクロ経済への含意を理解することは、依然として重要な課題となっています。
Irwin氏(カナダ銀行)は、固定金利型住宅ローンが経済の自動安定装置の役割を果たす可能性に着目し、住宅ローン市場が持つマクロ経済的な含意について論じました。分析では、住宅と住宅ローンを取り入れた異質的個人のニューケインジアン(HANK)モデルを用いて、固定金利型住宅ローンと変動金利型住宅ローンを持つ2つの異なる経済を考え、マクロショックに対するそれぞれの経済の反応を比較し、以下の3つの主要結果を報告しました。第1に、金融政策ショックに対して、固定金利型住宅ローンの経済は、変動金利型住宅ローンの経済よりも、マクロ経済変数の変動が小さくなる。第2に、固定金利型住宅ローンが安定装置として機能する度合いは、金融仲介機関の純利息マージンの変化によって生じる利潤もしくは損失が、同金融機関の株主である家計部門にどのように分配されるかに依存する。第3に、固定金利型住宅ローンは、供給主導型の景気後退に対しては経済の安定化に寄与するが、需要主導型の景気後退では必ずしもそうではない。
この研究は、金融政策ショックを含むマクロショックの波及が、住宅ローン市場構造に応じて、経済ごとに異なる可能性があることを示唆しています。特に、ショックの波及が、ショックによって生じる利益や損失が家計や金融仲介機関の間でどのように分配されるのか、に応じて変わり得るという点は、その分配に影響する市場構造や制度設計の重要性を示唆しています。
2. 安全資産を考慮した金融政策

標準的な現代マクロ経済モデルでは、簡単化のため、国債の供給がゼロであると仮定されることが一般的です。しかし実際には、多額の国債が発行され、投資家に保有されています。また、国債は、安全資産としても機能しています。こうした点を考慮すると、国債供給が正となるモデルは、標準的なモデルとは異なる政策的示唆をもたらす可能性があります。
この問いに答えるために、Brunnermeier氏(プリンストン大学)は、物価水準の財政理論、安全資産としての国債、および交換手段としてのマネーの3つの特徴を有する動学的モデルを構築しました。さらに、同モデルに経済主体として銀行を加えました。このモデルを用いて、金利と中央銀行のバランスシートを政策変数としたときの最適金融政策について分析し、以下の3つの主要結果を報告しました。第1に、金利の変化は、国債の評価額への影響を通じて、銀行を金利リスクにさらすため、中央銀行は、金利を設定する際に、実体経済とインフレの安定だけでなく金融安定も考慮する必要がある。第2に、量的緩和(QE)もしくは量的引締(QT)の影響は、取引される国債の満期によって異なる。第3に、金利調整を行う前に、銀行を含む民間部門が直面する金利リスクが事前に最適な水準になるように「予備的な(preparatory)QE/QT」を実施すると、後に実施される金利を政策変数とした金融政策の効果が高まり経済厚生も高まる、との結果が得られる。
本研究は、国債の満期構成は経済や政策効果にとって中立ではないこと、さらに、金融政策において金利リスクを考慮することの重要性を示しています。長期国債と銀行部門を現代マクロ経済モデルに導入することで、本分析は金融政策、特にバランスシート政策の役割に関し示唆を提供しています。
3. なぜ第二次世界大戦終期に米国の失業率は上昇しなかったのか?

失業率は、最大雇用を評価するために欠かせない指標であり、失業率と他のマクロ経済変数や政策との関係や、その動学を理解することは重要な論点です。歴史的な事象として、第二次世界大戦の終結時、政府支出とGDPが大幅に減少した一方で、米国の失業率は緩やかな上昇にとどまりました。具体的には、政府支出が70%、GDPが24%も減少したにも関わらず、失業率はピークでもわずか4%強にとどまりました。これはオークンの法則(Okun's Law)に反する結果です。
この事象を説明するという課題に取り組むために、Fujita氏(フィラデルフィア連銀)は新たにデジタル化された縦断的データセット(the Palmer data)を分析しました。具体的には、同データセットに含まれる各個人の属性データと全労働履歴、さらに、それに1940年代の政府調査データを統合して分析しました。その結果、以下の3つの主要な発見が得られました。第1に、戦争終期において、休暇や再教育のために退役軍人による労働市場への参入が遅れたこともあって、労働力人口が減少したことが、失業率の上昇が小さめにとどまったことに寄与した。第2に、労働力人口にとどまった労働者をみると、職を失った労働者の多くが失業することなくすぐに新しい職に就くことができ、そのような職から職への移動は産業間でも生じていた。第3に、新古典派モデルを通じてマクロ経済面をみると、戦時中に耐久消費財消費、住宅投資、設備投資が圧迫(クラウディングアウト)されたため、戦後にペントアップ需要を生み出し、大規模な財政ショックが示唆するよりもGDPの減少は抑制された。
本研究は、歴史的記録をデジタル化し、厳密な定量的分析を行うことの重要性を強調しています。大規模な労働市場の調整に例示されるような、過去の劇的な変動から学ぶことによって、現在、そして先行きの経済への理解をより深めることができます。
4. 生産性と市場の歪み:経済収束と実質為替レート

多くの国で、所得の高い国ほど物価水準が高い現象、いわゆる「ペン効果」が観察されています。そのため、所得が急激に増加する際には、相対的な物価水準を反映する実質為替レートの顕著な上昇が観察されます。しかし、東ヨーロッパ諸国はEUに加盟して以降、GDPが西ヨーロッパ諸国への明確な収束を示した一方で、2008年以降、実質為替レートは明確に増価することなく比較的安定的に推移してきました。
この謎を解明するために、藤原氏(慶應義塾大学/東京大学)は多国間・二部門の一般均衡モデルを構築し、1999年から2020年までの東ヨーロッパ12カ国の年次パネルデータを分析し、以下の主要結果を報告しました。第1に、理論的にはGDP成長と実質為替レートの関係は複雑であり、「修正版バラッサ・サミュエルソン効果」が成立する。すなわち、貿易財部門の生産性上昇は実質為替レートを増価させる一方で、貿易財・非貿易財両部門の生産性上昇はそれを減価させる。第2に、実証分析の結果、生産性上昇と労働市場の歪みが、長期の実質為替レートの動きを説明しており、修正版バラッサ・サミュエルソン効果が成立することが示された。さらに、生産性、労働市場の歪み、資本流入を考慮してモデルをシミュレーションすると、東ヨーロッパ諸国の実質為替レートの変動をうまく説明できた。
この研究は、長期の実質為替レートの決定要因について新たな視点を提供しています。特に、部門間における生産性上昇の違いや労働市場の歪みの重要性を示しています。同研究は、実質為替レートの増価なしに、GDPの収束が生じることも示しています。
* 文中の肩書はカナダ銀行・フィラデルフィア連銀・日本銀行共催ワークショップ時点のものです。
参考
これまでの「カナダ銀行・フィラデルフィア連銀・日本銀行共催ワークショップ」のニュースレター