2023年8月24日に、カナダ銀行とフィラデルフィア連邦準備銀行と共催でワークショップを開催しました(場所は、フィラデルフィア連邦準備銀行内)。
本ワークショップは、カナダ銀行と日本銀行との間で2013年に開始され、2019年からはフィラデルフィア連銀も主催者として参加することになりました。第6回目となる今回は、Matteo Iacoviello氏(連邦準備制度理事会)、Gauti Eggertsson教授(ブラウン大学)の2名の外部発表者を招待しました。
今回のニュースレターでは金融政策に関する発表論文のうち4本を紹介します[1]。
1. 労働市場と金融政策

Kurt See氏(カナダ銀行)は、転職行動がインフレ動学に果たす役割に関する研究を発表しました(論文名は、“Labor Market Shocks and Monetary Policy”)。
教科書的なマクロ経済学では、失業率が低下するほどインフレ率が上がります。いわゆる「フィリップス曲線」です。しかし、実際には、失業率が大きく低下してもインフレ率がさほど上がらない場合もあります。例えば、米国では、感染症拡大前の数年間、失業率の低下度合いに比べてインフレ率が上昇しないという現象がみられました。
通常、失業率が低下すると転職率が上昇しますが、この時期には上昇幅は限定的でした。See氏たちは、この点に注目し、理論モデルを用いて、転職行動の低下がインフレ率を抑制し得ることを指摘しています。就業者が転職するかどうかの意思決定を考えると、現在の勤務先から得られる賃金と転職した場合に得られる賃金を比較し、後者が高ければ転職すると考えられます。また、仮に転職が起きない場合でも、現在の勤務先からみると、転職先から高い賃金を提示される就業者は潜在的に引き抜かれるリスクがあります。理論モデルでは、就業者と現在の就職先との間で賃金の再交渉が行われると考えます。この結果、現在の雇い主が、より高い賃金を提示するのであれば、賃金は上昇します。賃金上昇は、物価上昇に帰結します。
分析では、感染症拡大前の2016年から2019年において、失業率は極めて低い水準となっていたものの、転職行動が低下していたことが物価の低迷(“missing inflation”)につながった可能性を指摘しています。著者たちは、2016年から2019年の間において転職行動がそれ以前と同様に発生していたのであれば、インフレ率は実績よりも25ベーシスポイントほど上昇していた可能性があると指摘しています。
2. フィリップス曲線の非線形性

インフレが進む米国では、労働市場のタイト化がみられています。Eggertsson教授は、極度の労働市場のタイト化がインフレ率を急激に大きく押し上げる―フィリップス曲線の非線形性―可能性についての分析を発表しました(論文名は、“It’s Baaack: The Surge in Inflation in the 2020s and the Return of the Non-Linear Phillips Curve”)。
分析では、求人数(job vacancies)を失業者数(unemployment)で割った指標(v/u)に注目します。労働市場がタイト化すると、求人が増え失業者は減ると考えられることから、この指標は上昇する性質を持つと考えられます。
米国の1960年から2022年について、この指標の推移をみると、現在のインフレ高進期を含め、v/uが1を上回る時期においては、他の時期と比べて労働市場の一段のタイト化に対して、インフレ率がより大きく上昇する傾向があります。これは、v/uが1のときを閾値とした非線形性の存在を示唆します。実際、計量モデルを用いてインフレ率とv/uの関係性を推計すると、v/uが1を上回るとインフレ率が非線形的に上昇することが確認されます。
分析では、次に、労働市場におけるサーチ・モデルと賃金の下方硬直性の考え方を用いて、非線形性の理論的説明を試みています。具体的には、失業者対比でみて求人が多いとき(v/u>1)には、企業がこぞって高い賃金を提示しあうことで賃金があがりますが、そうではないときには、労働者が賃金の切り下げを嫌うことから、仮に失業者がいたとしてもより多くの労働者を雇うために賃金を切り下げることはできない、と考えます。賃金がこのような非線形的な決まり方をする場合、インフレ率においても非線形性が生まれます。
こうした議論を踏まえ、著者たちは、現在の米国のインフレ率が労働市場のタイト化に起因すること、また、インフレ率を抑制するために犠牲にしなければならないGDPの低下幅が大きくない可能性があることを指摘しています。
3. 金融政策の同期と国際的な波及

現在、米国や欧州など、世界的なインフレ高進がみられており、これらの地域では政策金利が上昇サイクルに入っています。金利引き上げは、それぞれの国の総需要を抑制し、インフレ圧力を低下させることが期待されますが、経済活動がグローバル化している現在では、一国の政策金利の変更が、他国に影響を与える可能性もあります。
Iacoviello氏の分析は、この点を実証・理論面から検証しています(論文名は、“The International Spillovers of Synchronous Monetary Tightening”)。分析では、まず、21の先進国(“advanced economies”)の1980年から2019年のデータを用いて、他国の金利が上昇サイクルにあるタイミングで自国の政策金利を引き上げる場合と、そうではないタイミングで引き上げる場合とで、自国の実体経済に与える影響がどのように異なるのかを推計しています。推計結果からは、前者の場合、自国の実体経済の低下幅がより大きくなることが報告されています。
その理由として、著者たちは、グローバルな金融機関のグローバルな与信行動に注目します。例えば、自国の企業が、自国の金融機関と他国の金融機関の両方から与信を受けているとしましょう。自国の政策金利の上昇は、自国の金融機関の貸出金利の上昇を通じて、自国の経済行動を抑制しますが、他国の金融機関からの借入が可能であれば、その効果は低減されます。言い換えると、自国と他国が同時に金利上昇局面である場合には、この効果が生じないため引き締め効果が大きくなることになります。
金融取引は、実物取引に比べて規模が大きく、グローバル化も進んでいるほか、技術革新のスピードがはやく環境変化も大きいので、その金融政策の波及効果への影響は、引き続き注視する必要があります。
4. カナダの家計所得と金融政策
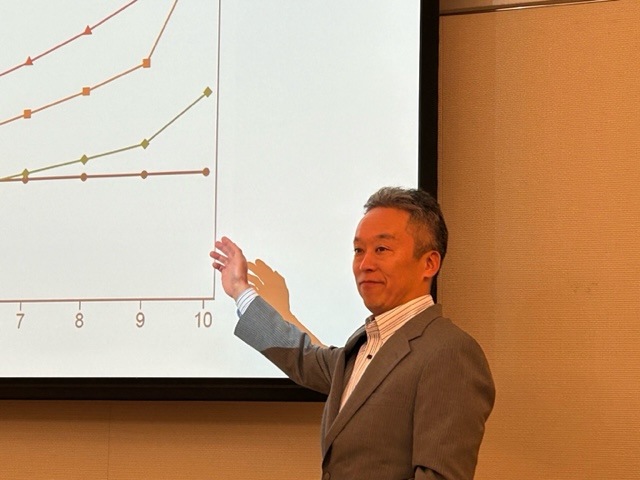
寺島康生氏(カナダ銀行)は、カナダの家計所得に関する税務データを用いて、家計の所得分布とGDPの関係性と、金融政策が家計の所得分布の形に与える影響について発表しました(論文名は、“Canadian Income Inequality and Monetary Policy”)。
金融政策が家計の所得の格差に及ぼす影響は、マクロ経済学において関心が高い分野で、米・欧・日を含め各国でそれなりに研究が存在するものの、現時点では、金融引き締めは所得格差を拡大させるという見方(例えば、失業者が増えるため)と、所得格差を縮小させるという見方(例えば、高所得者の資産所得が減少するため)がいずれも存在しており、定型的な見方は確立されていません。一つの理由としては、格差に影響を与える要因が、経済政策、景気循環、経済・社会構造など極めて多岐にわたることが考えられます。
本分析は、カナダ歳入庁によって集められた1982年から2019年までのカナダの確定申告者についての包括的なデータを用いており、寺島氏は、暫定的な結果としながらも、以下の2点を報告しています。①GDPと所得分布の関係をみると、GDPの上昇に対して、家計所得の平均値が上昇することに加えて、所得の分布の上半分の裾がより広がる形で拡大する。言い換えると、景気が改善すると、所得の分布がそのままの形で右にシフトするのではなく、極めて高い所得を持つ世帯が増えやすい。②所得水準ごとに家計を分けたうえで、それぞれのグループの所得と金融政策の関係をみてみると、引き締め的な金融政策がとられる場合、高所得の世帯が相対的に大きな所得の減少に直面する。言い換えると、所得格差が縮小する。
こうした家計の高粒度データを用いた分析は、格差自体の性質を知るうえでも極めて重要ですが、金融政策に対する反応が家計の属性ごとにどのように異なるのか、違いが何に起因するのかという点について知見を与えることを通じて、金融政策自体の波及経路についての一層の理解深耕にも資すると考えられます。
Notes
- このほか、フィラデルフィア連銀からはEnghin Atalay氏が“Gender Targeting in the U.S. Newspaper Ads: 1940-2000”、Wenli Li氏が“The Great Reshuffle: Residential Sorting During the COVID-19 Pandemic and Its Welfare Implications”という論文を、日本銀行からは須藤直が“Effects of Monetary Policy Shocks on Inequality in Japan”、小川泰尭が“Aging, Homeownership, and Macroeconomic Inefficiency”という論文をそれぞれ発表しました。 [1]
