金研設立40周年記念対談
中央銀行におけるリサーチ

第3回「コミュニケーションにおいて中央銀行リサーチが果たす役割」
-
第1回:中央銀行と学界の交流
-
第2回:金融政策運営における「アートとサイエンス」
第3回:コミュニケーションにおいて中央銀行リサーチが果たす役割
- 「中央銀行におけるリサーチ」のトップページに戻る
3回シリーズでお送りする、ウォルシュ教授、オルファニデス教授、若田部副総裁の対談の最終回です。中央銀行のリサーチは、中央銀行が人々とコミュニケーションをとっていくことにどう貢献できるかが議論されました。
今回の議論では、リサーチや政策運営を進めていくうえで国際的な相互交流が果たす重要性に焦点があてられました。
コミュニケーションにおける中銀エコノミストの重要な役割
若田部(日本銀行副総裁) 中銀エコノミストが理論とデータを理解し、それらを政策運営へ活用していくうえで大事なことを議論し、同様な考えを有していることが確認できました。
現代の金融政策運営において重要なもう一つの要素として、コミュニケーションがあげられます。多くの中央銀行はコミュニケーションや透明性を改善するために多くの努力を行い続けてきました。中央銀行のリサーチは、コミュニケーションの目的とどのように関連している、または有益だとお考えでしょうか?
オルファニデス (MIT スローン スクール オブ マネジメント 教授) はい。コミュニケーションは、中央銀行の内部に最新の学界の研究動向を理解する人材を持つべき、もう一つの重要な理由だと考えています。これには政策議論に直接応用できないような研究も含まれます。中央銀行がその責務を果たしていくためには、コミュニケーションに注力し、中央銀行が何をどのような理由で行っているかを説明していく必要があります。
中央銀行は往々にして、学界や世の中から「なぜこのような政策を行っているのか?」とか、「もっと別の政策を実行するべきだ」といった問いかけに直面します。このようなことが起きるのは、先ほど議論した学界におけるモデルの単純化に一部の原因があります。その単純化ゆえに、ある研究では実際の政策が意味をなさないように映るということが発生しえます。
このため、中央銀行は実行している事柄とともに、どうしてそのような運営方針を取っているのかを説明する必要があります。もっとも、こうした公共政策の議論に効果的に応えていくためには、学界の研究動向を理解したうえで、一般の人々に理解してもらえる言葉に翻訳できる中銀エコノミストを持つことが非常に重要になります。
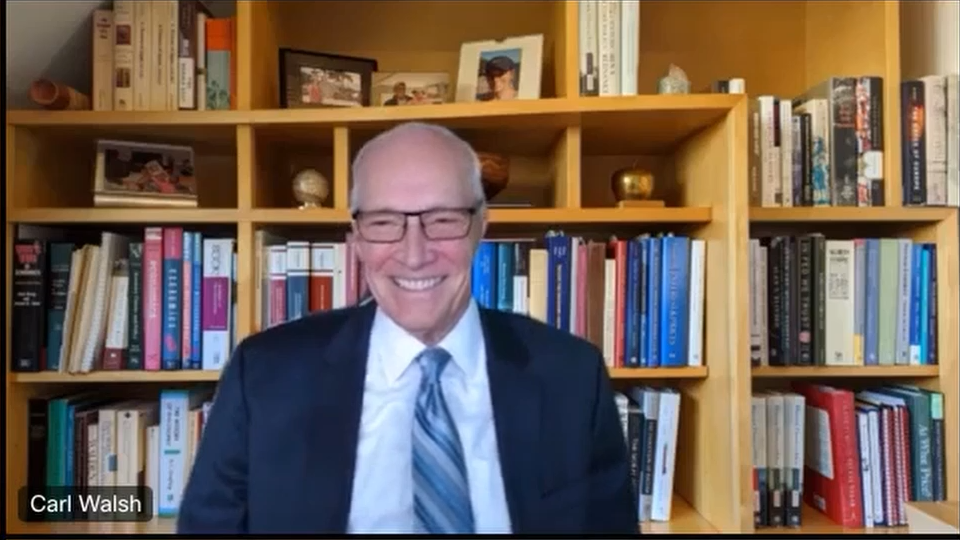
カリフォルニア大学サンタ・クルーズ校 特別名誉教授
ウォルシュ(カリフォルニア大学サンタ・クルーズ校特別名誉教授) シンプルにすること(keeping it simple)は、有益な金言です。文章執筆においてもスピーチにおいても常に心に留めておくべき金言です。
インフレ目標の大きな貢献のひとつは、まさに中央銀行が自身の政策をとても明快に説明する枠組みを与えたことだと考えています。おかげで、インフレとは何であるか、そして、なぜインフレを低く保つことが望ましいかを人々が理解できるようになりました。さらには、低位安定したインフレの達成という目標に対して中央銀行が行っていることがどう役立つのかという観点で議論を組み立てることができます。このことは、物事をシンプルに整理することに役立つでしょう。
近年の金融政策は信じられないほど複雑化していますので、人々が問題の複雑さを理解しきれないというリスクがあります。
コミュニケーションにおけるもう一つの重要なポイントは、達成できそうなことを過大に宣伝してはならないということです。先ほどアタナシオスが指摘したように、世の中には様々な不確実が存在しています。翌月や次の四半期に何が起きるかを正確に知ることは不可能です。そして、中央銀行が将来とるべき行動はそうした不確実性の影響を受けるのです。こうした複雑な状況を伝えていくことは難しいことです。それでも、中央銀行はそうした取り組みを試みていく必要があります。
オルファニデス 私もカールが指摘した点を強調したいと思います。私は、中央銀行のスタッフとリサーチャーには、家計や企業などの一般の人々に理解可能なものを「抽出」していってもらいたいと考えています。
研究者のコミュニティでは、専門用語が多用されますが、お互いが理解できる場合はよいでしょう。しかし、一般の人々と効果的なコミュニケーションを行うためには、テクニカルな言葉遣いではなく、平易な英語、平易な日本語を使っていく必要があります。
中央銀行内部で行われるリサーチは、政策当局者が発するメッセージをシンプルなものにすること、平易な言葉に翻訳することに役立ちます。このことをうまくやっていくのは恐ろしく難しいことですが、これまで以上に多くの資源を注ぐことでかなり改善していくことができると考えています。
ウォルシュ 私も同意見です。エコノミストでない聴衆とコミュニケーションをとることは重要な課題ですし、先ほど議論した人々の予想形成に関する問題とも関連しています。
異なる集団に属する人々がどのように予想を形成していくかをよりよく理解できれば、それぞれの集団に応じてコミュニケーションの取り方を工夫していくことが可能になるのでとても有益だと考えています。

誰に対しても同じ経済展望の講演をするのではなく、伝えたい内容に応じてどう異なる切り口で整理するか、この点に関する洞察を巡らせてみる余地があると思うのです。例えば、ニューヨークで市場参加者に対して講演する場合と、カリフォルニア州サンタ・クルーズの商工会議所で講演をするのでは、大きな違いがあるはずです。ですので、人々がどういったことに注目しており、どのように予想を形成しているのかをよりよく理解できれば、金融政策の影響に関心を持つ様々な人々すべてに対して、より明快なコミュニケーションを取れるようになるでしょう。
他国の経験からの学び
若田部 とても素晴らしいアイディアですね。ありがとうございます。中央銀行エコノミストは、優れた翻訳者であるだけでなく、優れたコミュニケーターでなければなりませんね。

日本銀行 副総裁
Fedが行った「Fed Listens」プログラム[15]では、Fedの人々にとって大きな驚きがあったと聞いています。多くの人々は名目値と実質値の違いを区別しておらず、とにかくインフレは全く好ましくないと考えていたそうです。人々は5%の名目賃金上昇率を期待しつつ同時に0%のインフレ率を望んでいました 。
政策運営においては、私たちはこのような人々の認識を念頭に置く必要があります。サーベイデータや経済主体の異質性を明らかにするデータは、おそらく私たちのコミュニケーション戦略の改善に役立つでしょう。
さて、この例は、政策当局者が自国の一般の人々とのコミュニケーションから多くのことを学べることを示していると思います。そして、国際的な相互交流についても同様のことが言えるのではないかと考えています。
オルファニデス まさに、国際的な相互交流は非常に有益なことです。バーゼルの国際決済銀行(Bank for International Settlements: BIS)での様々な会合はその好例です。
金融安定上の問題を議論するとき、必ず出てくる問いは「何が金融安定達成に向けたベストプラクティスなのか?」というものです。各国に共通する要素もあるでしょうし、各国の特徴や経済構造に依存する別の要素もあるでしょう。
各中央銀行が自国の特性をよく理解したうえで、他国の中央銀行の政策担当者やリサーチャーとそれぞれの経験について議論しあい、教訓を「抽出」していくことは極めて価値のあることです。こうした取り組みは、ベストプラクティスを明らかにし、グローバルな規制の枠組みを構築することに役立ちます。

ウォルシュ 名目金利のゼロ金利下限(ゼロ金利制約)に関する初期の研究においても、同様の事例がありました。日本がゼロ金利制約に直面した頃は、他国はまだそれを心配する必要がない状況でした。その結果、ゼロ金利制約に関する多くの貢献は日本人や日本で活動している研究者によってもたらされました[16]。
このように、ある国が直面した問題は、しばしば、他国の政策当局者にとってものちに問題になりえます。
このことは、学界においても政策リサーチにおいても、国際的な経済学研究者コミュニティを形成し、意見交換や経験の共有を行っていくことが重要である一つの理由になっています。
オルファニデス カールの見解に同意します。われわれが様々な困難に直面するとき、それらの困難はしばしば共通点を持っています。このため、先に困難に直面した国々の経験から学ぶことはとても重要なことです。
第二次世界大戦後にゼロ金利制約の問題に初めて直面した日本は、そのもっとも顕著な実例といえるでしょう。
ウォルシュ ただ、一つ注意しなければならないことがあります。経済学の論文は英語論文が圧倒的多数を占めており、モデルも多くの場合は米国のデータに基づいたものや、米国のデータを説明しようとするものです。米国が対象の場合についても、非常に定型化されたモデルが用いられています。
このことは、例えばFedやECB以外の中央銀行に所属するエコノミストに重要な役割があることを意味します。すなわち、経済学の論文で扱われているモデルが、個別の国々の描写としてどこまで妥当性があるのかを検討するという役割です。
例えば、日本の政策を導き出すためのモデルに米国のデータに合うように調整されたモデルを持ち込もうとすることは適切ではありません。この点は、米国やEU、日本といった(規模や内需が大きな自由資本主義)経済以外の場合により深刻な問題となります。このため、先行研究のモデルが個々の国の分析に適切なものかどうかを考えることが出来るリサーチャーをもつことが大事です。
それと同時に、日本のような国では、金融政策を考えるうえで考慮しなければならない国内要因があるでしょう。そうした日本の国内要因は、米国の経済学者は研究対象とはしないでしょう。このため、日本の研究者がこうした国内特有の問題に取り組むことがとても重要だと考えています。
日本の研究コミュニティからの貢献
若田部 その通りですね。ところで、カールは見事に私が用意していた最後の質問に話を展開してくれました。それは、非日本語圏の聴衆に向けたコミュニケーションをより効果的なものとするために、日銀のエコノミストができることは何であろうかということ、そして、日本発の研究トピックとしてどのようなものが関心を呼ぶものだろうかということです。
すでにお二人が言及されている通り、ゼロ金利制約はその一例かと思いますが、他にも日本国外の聴衆が興味を持つテーマがあるのではないかと思っています。

MIT スローン スクール オブ マネジメント 教授
オルファニデス まさに、ゼロ金利制約はとてもよい例で、引き続き日本の経験から教訓を得ています。その他に、日本が最前線に立っている重要な問題としては、高齢化社会に関連する課題や、そうした人口動態が労働市場の動向に与える影響です。
データ面については、短観に一言触れたいと思います[17]。短観は非常に充実したサーベイデータであり、とても有用なものなので、他国の中央銀行も参考にすべきだと考えています。私自身、Fedに在籍していた1990年代のころからすでに、日本の景気動向の評価に短観を活用してきました。
とはいえ、繰り返しにはなりますが、人々がどのように考え、経済をどのように認知しているかを理解するためには、今ある以上により多くのデータを使っていく必要があると考えています。
ウォルシュ 前のところのデータに関する議論で、人々の予想についての分布情報の有用性について強調しました。この分野は、日本が様々な取り組みを行ってきた分野です。
例えば、日銀のエコノミストは、テキスト分析手法を使って予想に関するサーベイデータを分析した研究などを行っています[18]。この研究は、サーベイの回答者がある質問を問われたときに、どういう問いに自分が答えていると認識しているのかを明らかにしようとしたものです。これはかねてより重要な問題であって、この研究はより多くの人々の関心を集めるべき研究だと考えています。
若田部 何とも勇気づけられるお言葉です。
オルファニデス リサーチを進めていくほかにも、金研は国際コンファランスを開催することで政策リサーチ・コミュニティに貢献しています[19]。国際コンファランスは、学界と政策サイド双方の人が集い、日銀のスタッフも含めて交流を図れる非常に成功したフォーラムになっていると感じています。
若田部 その通りですね。私も、政策パネルの議論にときには議長として、ときにはパネリストとして参加しましたが、いずれも高い見識を持つ政策当局者や研究者の方々と意見交換できる素晴らしい機会であったと感じています。
オルファニデス 今日の議論もとても楽しかったです。心残りがあるとすれば、今日の議論はできれば対面で行いたかったですね。コーヒーブレイク中の気軽な会話や、コンファランス・プログラムの合間の議論を再びできるのが待ち遠しいです。
ウォルシュ 対面での交流は非常に重要ですね。2020年の国際コンファランスは、新型コロナウイルス感染症のために中止になってしまいましたし、2021年と2022年のコンファランスはオンライン開催でした。来年(2023年)は対面開催ができるとよいですね。

若田部 私も、できれば去年や今年も対面でコンファランスを開催したかったです。2023年は対面のコンファランスを開催することになりました。そして、カールが今年(2022年)の年末で金研海外顧問を退任されるため、来年のコンファレンスにいらっしゃらないのを、私を含め一同本当に寂しく思います。この場を借りて、日本銀行を代表して、これまでの金研への多大なサポートと貢献に感謝いたします。
そして、本日の素晴らしい議論にも感謝いたします。お陰様で、金融政策運営やリサーチに関する様々な重要トピックについて、とても充実した意見交換ができました。では、近々対面でお会いできる日が来ることを楽しみにしております。本日はどうもありがとうございました。
<終>
Notes
- 「Fed Listens」の取組みの中で、Fedは15回の広聴イベントを開催し、労働組合や、中小企業経営者、退職者の団体などを含む様々な団体と意見交換を行った。詳細については、次のウェブサイトを参照。 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/review-of-monetary-policy-strategy-tools-and-communications-fed-listens-events.htm [15]
-
ゼロ金利制約に関する日本人を含めた経済学者による初期の貢献としては、例えば次の論文を参照。
Jung, Taehun, Yuki Teranishi and Tsutomu Watanabe (2005) "Optimal Monetary Policy at the Zero-Interest-Rate Bound," Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 37(5), 813-835. [16] -
短観(全国企業短期経済観測調査)は、日本銀行が実施している四半期のサーベイ調査。現在、約1万社程度の日本の民間企業を対象に、判断項目(業況、需給、販売価格・仕入価格など)や、年度計画(売上高、経常利益、設備投資額など)の様々な項目を調査している。また、2014年に、企業の物価見通しに関する調査項目を新設した。調査結果や詳細な情報については次のウェブサイトを参照。
https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/tk/extk05.htm [17] -
例えば、Nakajima et al. (2021) や、短観調査における企業の物価見通しのサーベイデータに関する研究(Uno, Naganuma, and Hara, 2018a, 2018b、稲次・北村・松田(2019))を参照。
Nakajima, Jouchi, Hiroaki Yamagata, Tatsushi Okuda, Shinnosuke Katsuki, and Takeshi Shinohara (2021) “Extracting Firms' Short-Term Inflation Expectations from the Economy Watchers Survey Using Text Analysis,” Bank of Japan Working Paper Series, No.21-E-12.
Uno, Yosuke, Saori Naganuma, and Naoko Hara (2018a) “New Facts about Firms' Inflation Expectations: Simple Tests for a Sticky Information Model,” Bank of Japan Working Paper Series, No.18-E-14.
Uno, Yosuke, Saori Naganuma, and Naoko Hara (2018b) “New Facts about Firms' Inflation Expectations: Short- versus Long-Term Inflation Expectations,” Bank of Japan Working Paper Series, No.18-E-15.
稲次春彦・北村冨行・松田太一(2019)「企業のインフレ予想の形成メカニズムに関する考察―短観データによる実証分析―」、日本銀行ワーキングペーパーシリーズ、No.19-J-9.
このほか、日本銀行では、オルタナティブデータや、テキスト分析手法を含む機械学習を利用した様々な分析を行っている。これらの研究の一覧については、次のウェブページを参照。
https://www.boj.or.jp/research/bigdata/index.htm [18] -
金融研究所は1983年より、国際コンファランスを開催している。詳細については次のウェブページを参照。
https://www.imes.boj.or.jp/conference.html [19]

カール・E・ウォルシュ
カリフォルニア大学サンタ・クルーズ校特別名誉教授。1976年カリフォルニア大学バークレー校博士課程修了。Ph.D.(経済学)。サンフランシスコ連邦準備銀行シニアエコノミストなどを経て、1991年カリフォルニア大学サンタ・クルーズ校教授、2010年同特別教授、2020年より現職。2019年~22年に日本銀行金融研究所海外顧問。ご専門は金融論・中央銀行論など。主な著書にMonetary Theory and Policy (Fourth edition, MIT Press, 2017)。

アタナシオス・オルファニデス
マサチューセッツ工科大学(MIT) スローン スクール オブ マネジメント教授。1990年MIT博士課程修了。Ph.D.(経済学)。米国連邦準備制度エコノミスト、同シニアアドバイザーを経て、2007年キプロス中央銀行総裁に就任。欧州中央銀行政策理事会メンバー 、欧州システミックリスク理事会運営委員を兼任した。2018年より日本銀行金融研究所海外顧問。ご専門は、中央銀行論、ファイナンス、政治経済学。

若田部昌澄
日本銀行副総裁。1990年早稲田大学大学院修士課程修了、1994年トロント大学経済学大学院修士課程修了。早稲田大学政治経済学部専任講師などを経て、2005年同政治経済学術院教授、2017年コロンビア大学経営大学院日本経済経営研究所客員研究員、2018年3月より現職。経済思想史が専門で、大恐慌をはじめとする経済危機に関する論文・著書多数。
- 本対談は、2022年11月中旬に開催しました。文中の肩書は対談時点のものです。
- 本ニュースレター中で示された意見・見解は登壇者のものであり、登壇者が現在所属している、または過去に所属していた組織の公式見解を示すものでは必ずしもありません。
- " Basel - Bank für internationalen Zahlungsausgleich1.jpg ” (2ページ目掲載の国際決済銀行本部の写真)は、Taxiarchos228によるもので、Licence Art Libre Free Art License 1.3 ライセンスのもと配布されています。