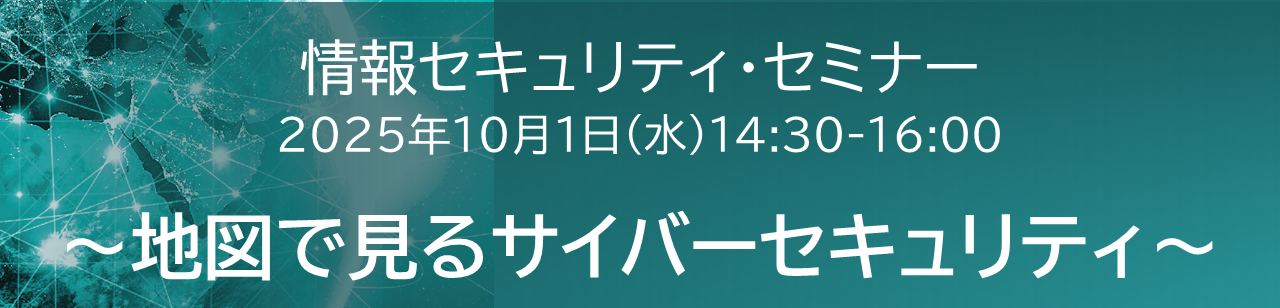情報セキュリティ・セミナー
「地図で見るサイバーセキュリティ」
日本銀行金融研究所
情報技術研究センターでは、10月1日(水)、「地図で見るサイバーセキュリティ」をテーマとして、情報セキュリティ・セミナーを開催しました。
近年、国家間の対立や紛争を背景とした、地政学リスクに起因するサイバー攻撃が増加しています。サイバー空間は、これまで物理空間とは独立した空間として認識されていましたが、物理空間におけるリスクがサイバー空間に与える影響は少なくないことが明らかになってきています。また、サイバー攻撃を観測することにより、攻撃の地理的傾向を可視化する研究も進められています。
重要インフラである金融分野においては、こうしたサイバーセキュリティの動向を適時に把握したうえで、適切な対策を講じることが求められます。本セミナーでは、物理空間とサイバー空間の関係に焦点を当て、サイバー攻撃の地政学リスクとの関係や地理的傾向について、第一線の研究者より最新の動向をご講演いただきました。
1.日時および開催形態
-
(1) 日時
-
(2) 開催形態
オンライン開催(Cisco Webex Webinarsを利用)
2.プログラム
-
川口貴久 氏(東京海上ディーアール株式会社・主席研究員)
概要:サイバー空間では様々な階層や争点で国家間の競争が繰り広げられています。海底ケーブルやデータセンターなどの物理インフラ層でも同様の競争が展開され、物理的な攻撃・影響のリスクもあります。そこで、本講演ではウクライナ戦争や台湾海峡をめぐる潜在的紛争を例に、物理インフラ層に焦点を当てたサイバー空間の地政学的リスクを紹介します。
-
笠間貴弘 氏(情報通信研究機構<NICT>サイバーセキュリティ研究室・室長)
概要:本講演では、NICTサイバーセキュリティ研究室における大規模なサイバー攻撃観測で得られた観測データに基づき、最新のサイバー攻撃の傾向や代表的な事例について紹介します。特に、IoTマルウェアの大規模感染事例や分散反射型サービス妨害(DRDoS)攻撃などを取り上げ、それらに見られる地理的な傾向の有無や、詳細な分析結果を共有します。併せて、これらの脅威に対するNICTでの最新の研究開発の取組状況について紹介します。
3.模様
4.照会先
日本銀行金融研究所情報技術研究センター
E-mail:citecs(at)boj.or.jp(メールアドレスの(at)は@に置き換えてください)