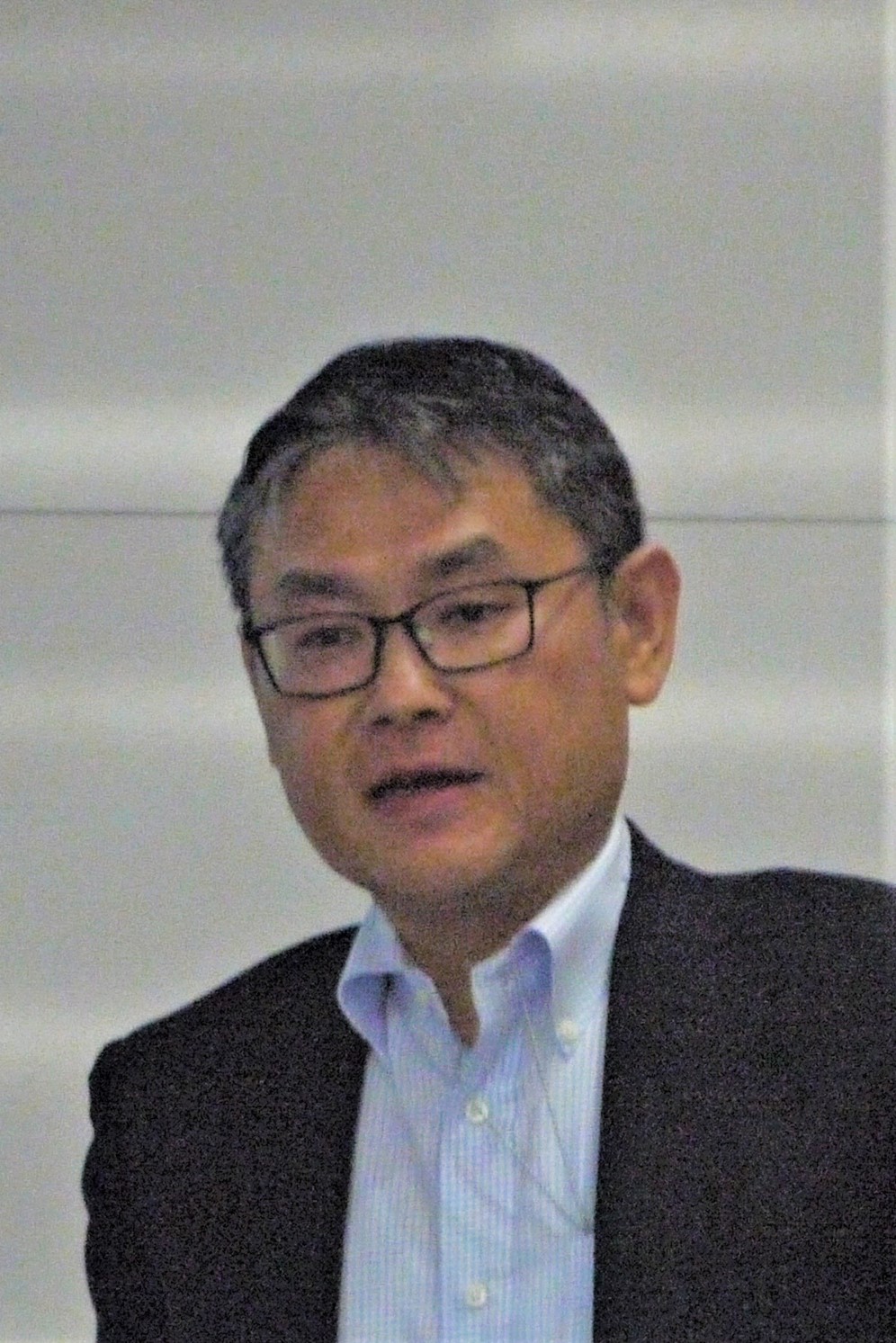日本銀行金融研究所では、5月27日~28日に2025年国際コンファランスを開催しました。1983年に第1回を開催して以降、今回で30回目を迎えました。各国中央銀行、国際機関、学界等から約90名が参加し、「金融政策の新たな課題」をテーマに、講演、論文報告、特別対談、パネル討論が行われ、政策運営から経済分析まで幅広く議論されました。 [Program]
1. 開会挨拶
植田和男総裁(日本銀行)は、わが国の金融政策が直面している課題について、講演しました。最初に、日本の物価上昇率の現状について、説明しました。2021年以降、日本の物価上昇率は米欧に遅れて高まったのち、足もとでは食料品価格の上昇につれて、再び上昇している、と述べました。
次に、日本の政策金利は日米欧経済のなかで最も低くなっていると述べました。そうしたもとで、「実際の物価上昇率が 2%を上回って3年以上推移しているにも関わらず、なぜ日本銀行はそのような緩和的なスタンスを維持しているのか」と問題提起したうえで、基調的な物価上昇率がなお2%を下回っているためと答えました。
続いて、基調的な物価上昇率を捉える完璧なデータは存在しないと述べたうえで、基調的な物価上昇率を評価するために注意深くモニターしている指標のひとつとして、予想物価上昇率を挙げました。日本の予想物価上昇率は、1.5%から 2.0%の間にあり、2%の目標水準を下回っていると述べました。それを2%にアンカーするために、緩和的な政策スタンスを維持し続けている、と説明しました。
また、この政策スタンスのコミュニケーションは容易ではないと指摘しました。その理由として、人々が注目する総合ベースでみた物価上昇率と、中央銀行が注目する基調的な物価上昇率との間に大きな乖離があることを挙げました。サプライショックが頻繁に生じるようになるにつれて、こうした乖離は、多くの中央銀行にとって主な焦点であり続けると考えられる、と述べました。
最後に、本コンファランスの議論が、基調的な物価上昇率と予想物価上昇率の計測、それらに支えられた金融政策についてのコミュニケーションのあり方、頻繁に生じるサプライショックのもとでの金融政策運営などの極めて重要な問題に光を当て、世界の中央銀行コミュニティに貴重な知見がもたらされることを祈念すると述べ、開会挨拶を結びました。
【次ページ】前川講演
前のページへ
2. 前川講演
アグスティン・カルステンス総支配人(国際決済銀行)は、数多くの経済・金融危機に対峙してきた経験をもとに、公共政策に対する信頼(trust)の重要性に関する講演を行いました。
まず、数多くの危機から得られた2つの重要な教訓を挙げました。第1に、危機の代償は大きいため回避することが最善である、と述べました。第2に、経済と金融市場は常に変化するため、現在適切と思われる政策や枠組みも、最終的には、おそらく急速に変わる必要がある、と述べました。
続いて、信頼の重要性を強調しました。国民が政策当局の行動を信頼している場合、国民は、そのような行動を前提に経済活動を行うようになることに加えて、短期的なコストを伴うものの長期的な利益を生む政策的措置をより受け入れてくれるようになると説明し、信頼は政策の有効性と正当性を支えるものだ、と述べました。
さらに、信頼のダイナミクスには好循環があると述べ、効果的で正当性のある政策は当局の目標達成を容易にし、それはさらなる信頼の蓄積へとつながり、好循環が生まれると説明しました。しかし、このダイナミズムは逆の方向にも働く可能性があると警告し、信頼を維持することは絶え間ない課題だと述べました。さらに、マクロ経済政策が持つ様々な側面、特に金融政策、金融システムの安定に係る政策、財政政策への信頼は、相互に密接に関連している、と強調しました。
最後に、政策立案者があらゆる課題について特例的な政策を行うと期待させることは、国民の信頼を損なうことに繋がっていくと指摘し、強い耐性と頑健性を備えた経済と金融システムを構築していくことが、政策を効果的にする最善の方法だと述べて講演を締めくくりました。
【次ページ】基調講演
前のページへ
3. 基調講演
アタナシオス・オルファニデス教授(マサチューセッツ工科大学、金融研究所海外顧問)は、シンプルな政策ルールを取り入れることで、政策の枠組みがどのように改善され得るかを論じました。
最初に、金融政策とそのコミュニケーションが直面する課題として、見せかけの知識と裁量への傾向という相互に関連する2つを取り上げました。
続いて、シンプルな政策ルールが持つべき望ましい性質について述べました。具体的には、中央銀行の目標と整合的な形での物価安定の維持と景気循環の一定程度の平準化に資することに加えて、情報の不完全性に対して頑健であることが望ましいと述べました。
次に、米国のリアルタイムデータと予測データを使用し、実例として挙げたシンプルな政策ルールは、2019年までの米国の政策金利の推移を概ね捉えられることを示しました。しかしながら、2021年と2022年初には、実際の政策と大きな乖離があったことを指摘しました。これは、ルールによるガイダンスがあれば、連邦準備制度(Fed)は政策金利を長期にわたって低位に据え置いたことを避けることができたであろう事例だと述べました。
最後に、政策ルールを伝えることの主な利点をまとめ、講演を締めくくりました:①ルールは、中央銀行に対する信頼を築き、政策上の大きな誤りを避ける上で有用であり、システマティックな政策を推進できる、②ルールは、状況が許すもとでの裁量的な行動を排除するものではなく、裁量を説明することに重きを置くものである、③ルールが示唆する政策金利のリアルタイムの公表は、見通しの推移に明示的に紐づけられた政策金利に関するガイダンスにもなることから、中央銀行のコミュニケーションを改善できる。
【次ページ】特別対談
前のページへ
4. 特別対談
特別対談の司会を務める氷見野良三副総裁(日本銀行)が、ジョン・ウィリアムズ総裁(ニューヨーク連邦準備銀行)をゲストとして迎えて、対話のなかでいくつかの問いを投げかけました。
それらに対して、最初に、ウィリアムズ総裁は不確実性が高いもとでの金融政策運営について論じ、ある経済モデルにおいて最適な政策が、別のモデルでは非常にパフォーマンスが悪くなることがある、と指摘しました。したがって、高い不確実性に直面するもとでは、最適解を見つけるのではなく、複数のシナリオ下でうまく機能するアプローチを考える方がよい、と述べました。
次に、インフレ予想について議論しました。コロナ禍以前を振り返り、それまでの数十年間、米国のインフレ率が低位で安定していたことが、インフレ予想の形成に大きな影響を与えた、と論じました。そのうえで、コロナ禍以降の5年間で、インフレに対する人々の認識が変化し、以前に低インフレを経験した世代のインフレ予想の分布が上方向にシフトした、と指摘しました。これらを踏まえ、インフレ予想は望ましくない方向に変化する可能性があり、インフレ予想がしっかりとアンカーされていることを当然視すべきではない、と注意を喚起しました。
次に、自然利子率に議論を転じ、グローバルな要因が自然利子率に与え得る影響について論じました。AIの普及等は生産性の伸びを押し上げるため、自然利子率を押し上げる可能性がある一方、貿易政策の変化といったその他の要因は自然利子率を押し下げ得ると考えられるものの、どちらの影響が大きいかを予測することは困難だ、と説明しました。
最後に、2025年4月に生じた資産価格のボラティリティの急激な高まりを振り返り、通商政策をめぐる発表が米国市場に大きなショックを与えたとしながらも、市場は機能不全には陥らなかったと述べました。そして、「現金への逃避(dash for cash)」がみられた2020年3月とは大きく状況が異なっていたと述べ、レポ市場でも無担保コール市場でも特に問題は生じなかったと指摘しました。
【次ページ】論文報告セッション
前のページへ
5. 論文報告セッション
論文報告セッションでは、物価や金融政策に関する理論的・実証的な研究が計4本報告され、討論者とフロア参加者も交えて活発な議論が展開されました。
【次ページ】政策パネル討論
前のページへ
6. 政策パネル討論

今回のコンファランスのテーマ「金融政策の新たな課題」に合わせて、「不確実な経済」と「グローバル経済」をテーマとした2つの政策パネル討論が行われました。
「不確実な経済」をテーマとしたパネル討論では、星岳雄(教授、東京大学、金融研究所特別顧問)が座長を務め、マリオ・センテノ(総裁、ポルトガル銀行)、アンドリュー・ハウザー(副総裁、オーストラリア準備銀行)、ニール・カシュカリ(総裁兼CEO、ミネアポリス連邦準備銀行)、M・アイハン・コーゼ(副チーフエコノミスト兼見通し局長、世界銀行グループ)の4名のパネリストが討論を行い、不確実性が高まるもとでの金融政策の課題について議論しました。






「グローバル経済」のパネル討論では、クリストファー・ウォラー(理事、連邦準備制度理事会)が座長を務め、ピエール=オリヴィエ・グランシャ(経済顧問兼調査局長、国際通貨基金)、リュック・ラーフェン(調査局長、欧州中央銀行)、クレア・ロンバルデッリ(副総裁、イングランド銀行)、エリ・レモロナ Jr.(総裁、フィリピン中央銀行)、内田眞一(副総裁、日本銀行)の5名のパネリストが、グローバル経済における金融政策について議論しました。






* 文中の肩書は国際コンファランス時点のものです。