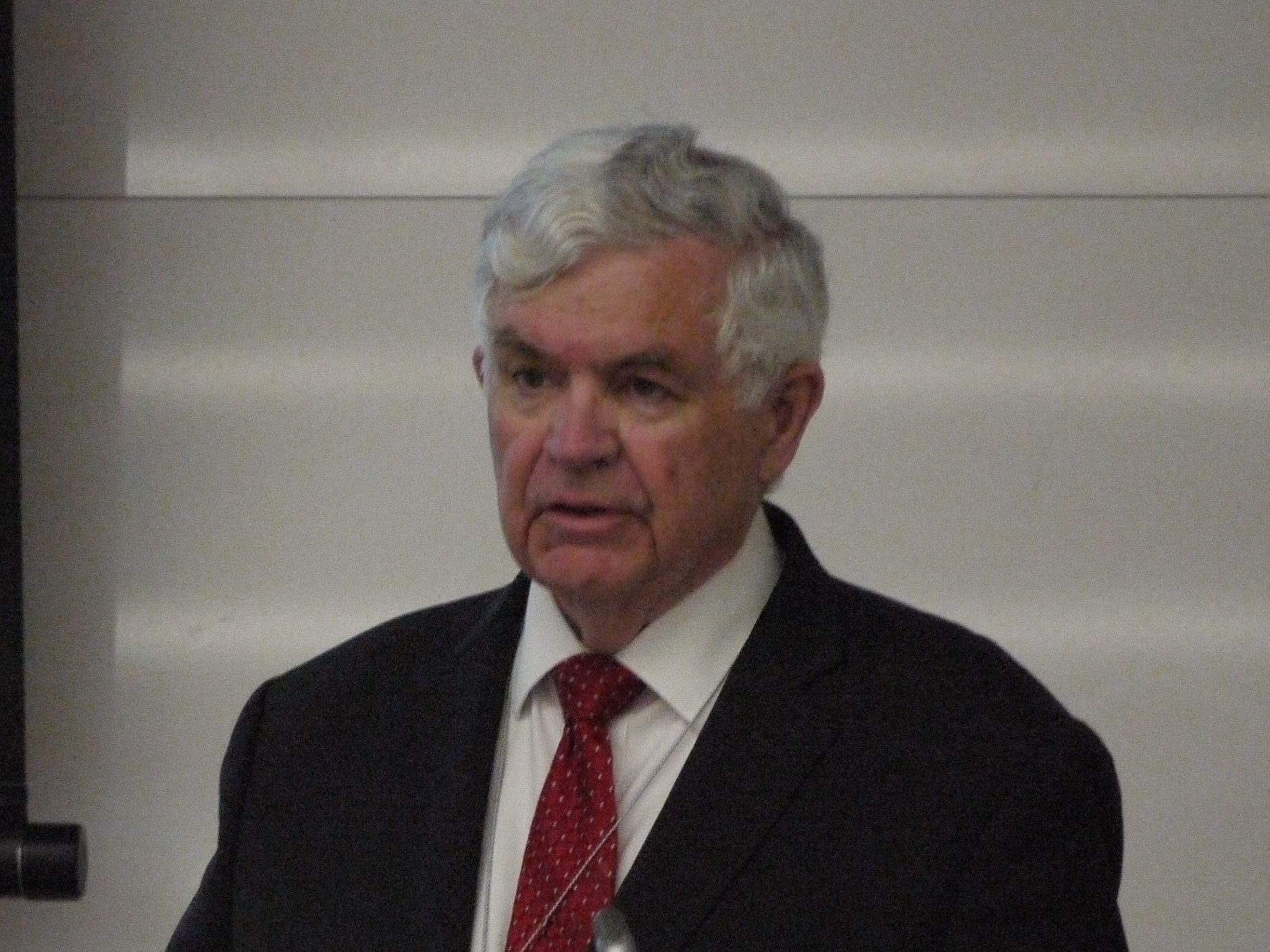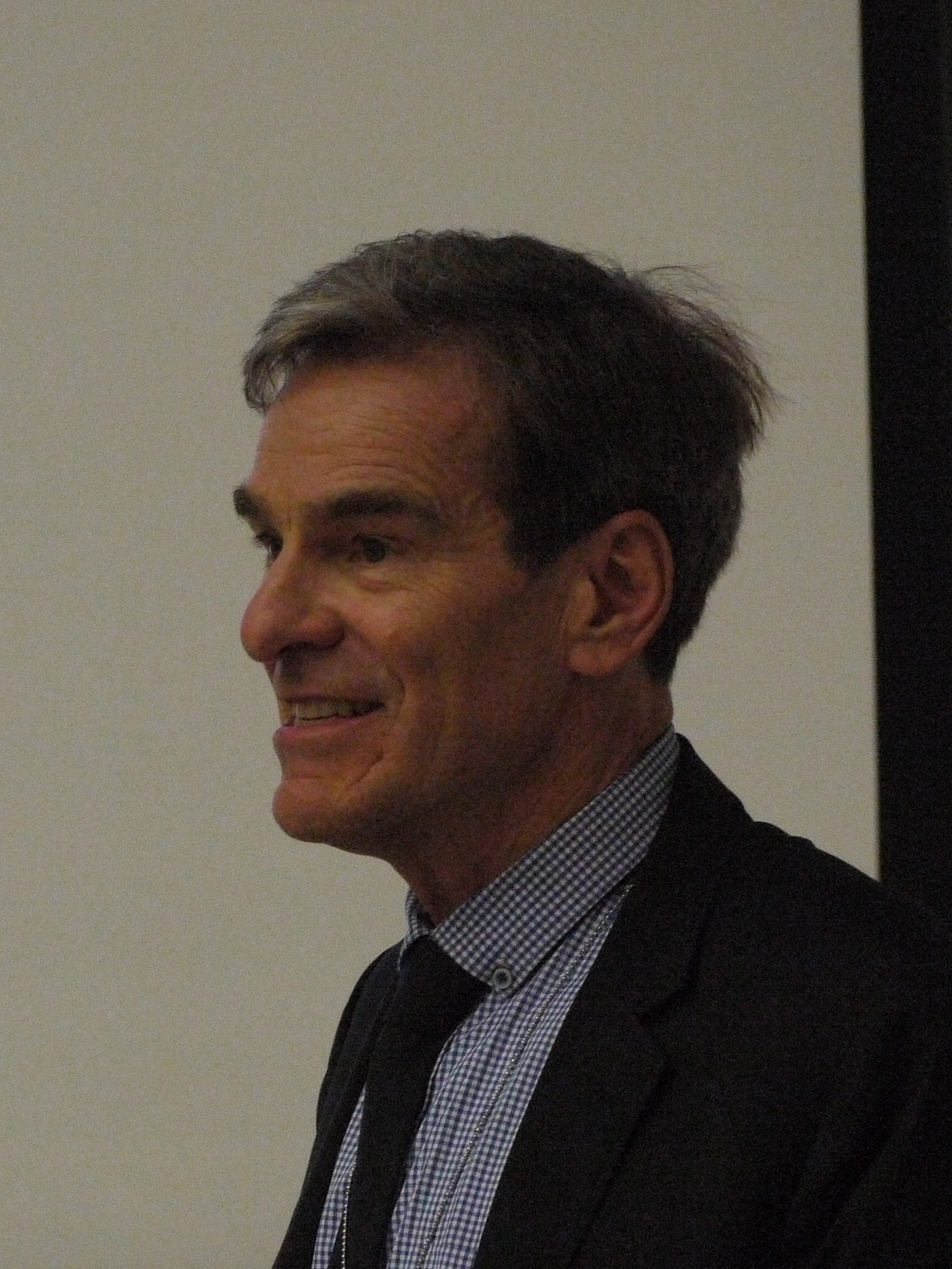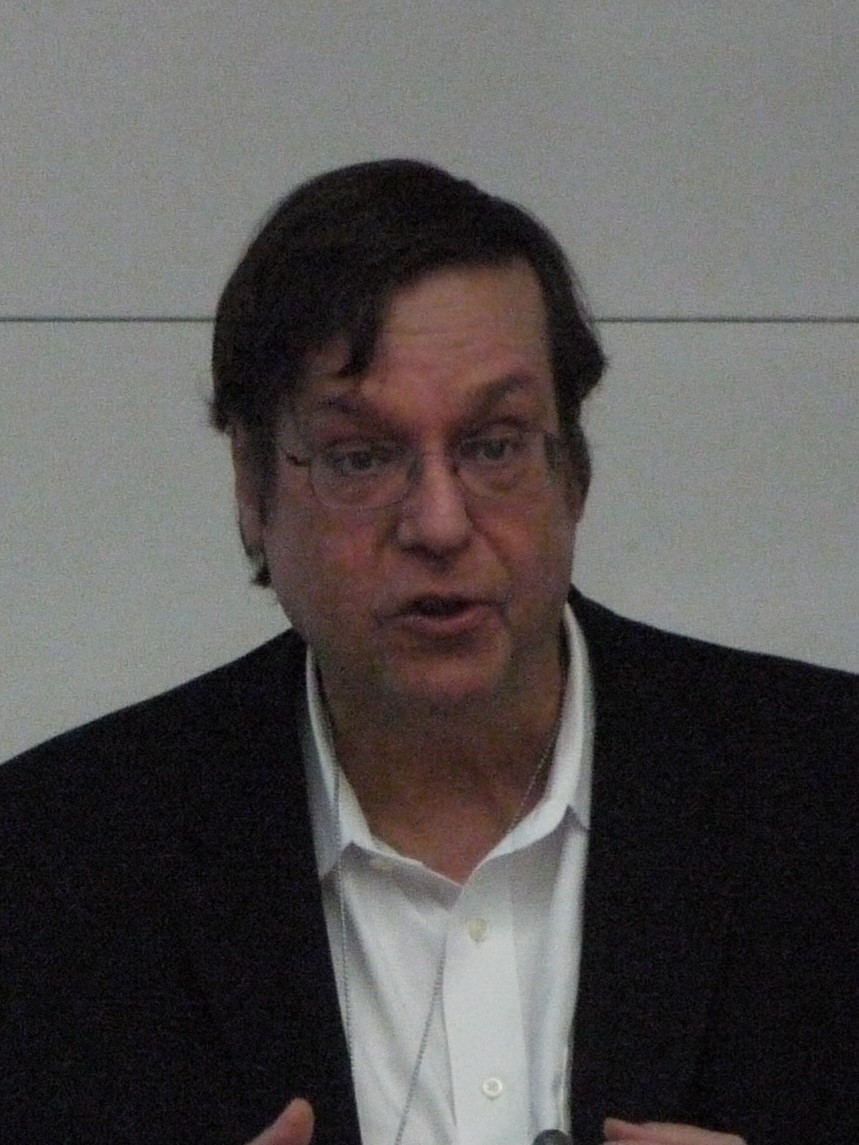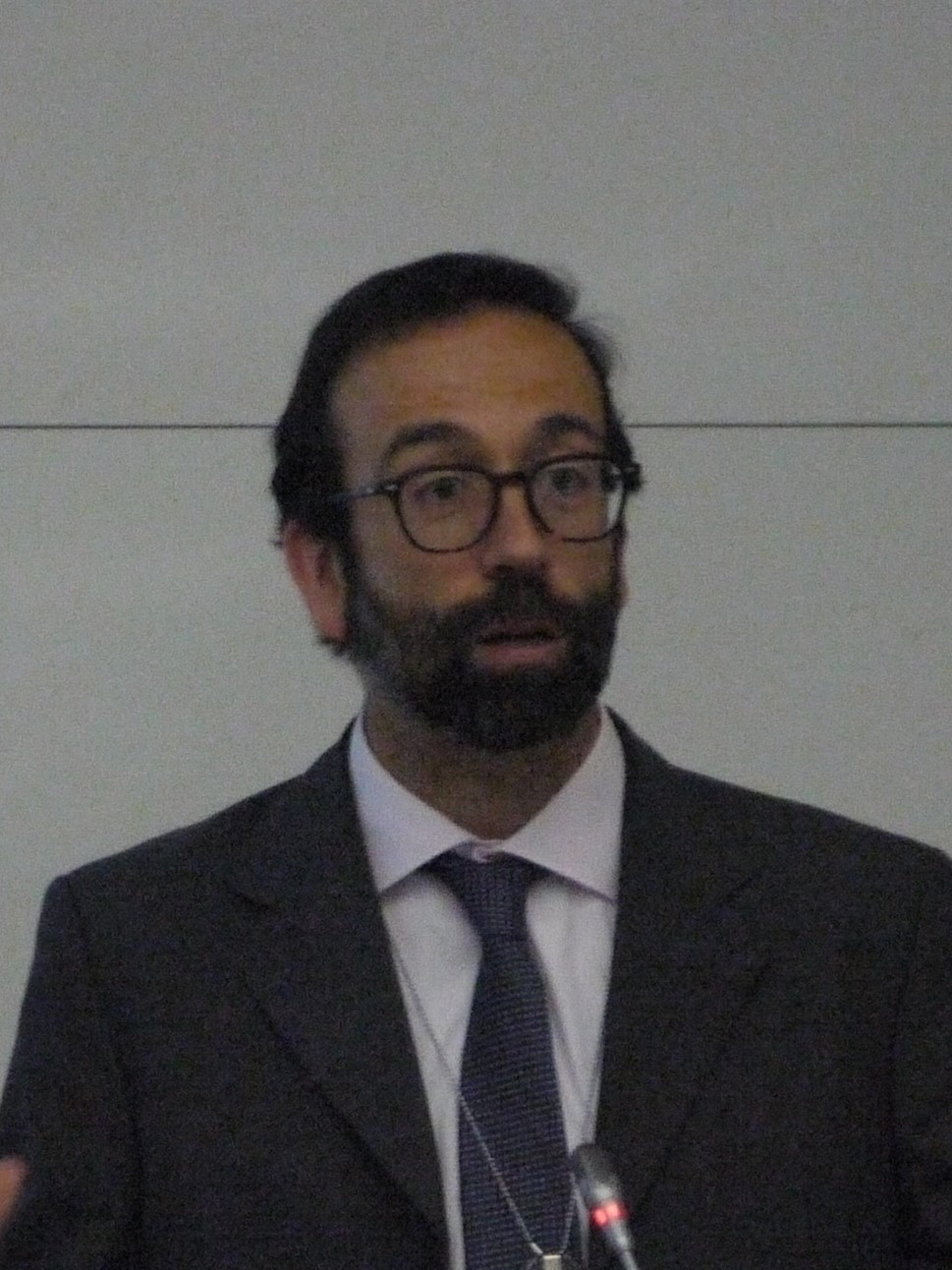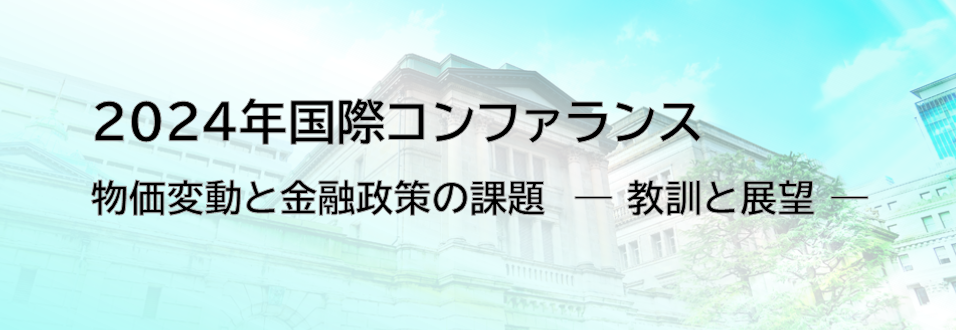
日本銀行金融研究所では、5月27日~28日に2024年国際コンファランスを開催しました。1983年に第1回を開催して以降、今年で29回目の開催となった今回は、日本銀行の金融政策の「多角的レビュー」の一環としても位置付けられており、多くの海外中央銀行の総裁をはじめ、各国中央銀行、国際機関、学界から100名ほどの参加者がありました。コンファランスでは、「物価変動と金融政策の課題 -- 教訓と展望 --」をテーマに、物価変動ダイナミクスと伝統的・非伝統的金融政策に関する講演、論文発表、パネル討議が行われ、活発な議論が展開されました。 [Program]
1. 開会挨拶
植田和男総裁(日本銀行)は、コンファランスの導入として、日本銀行が3月に実施した金融政策の枠組みの見直しに言及した後、過去25年間について振り返りました。
まず、日本が、1990年代後半から「ゼロ・インフレの罠」に陥った主たる理由として、「ゼロ金利制約(Zero Lower Bound: ZLB)」を挙げ、ゼロ・インフレの罠が始まるまでには、日本銀行は、経済を刺激するための短期金利に対する影響力を既に使い切ってしまっていた、と指摘しました。
また、日本銀行が困難に直面したもう一つの理由として、低インフレが持続するという予想が定着したことを挙げ、これが、経済主体の行動変化、とりわけ、企業の戦略的な価格設定行動の変化につながり、ゼロ・インフレの罠に陥っている期間を長引かせることになった、と指摘しました。
最後に、昨年から今年にかけて、世界的なインフレとそれまでの金融緩和の枠組みが維持されたもとで、賃金が急速に上昇していったことに触れました。続けて、これまでのところ、インフレ予想をゼロ%から押し上げることには成功したようにみえるものの、今後は、それを2%の目標値にアンカーしなければならない、と述べ、日本銀行は、その実現に向けて注意深く進んでいくつもりだとして、開会挨拶を結びました。
【次ページ】前川講演
前のページへ
2. 前川講演
ジョン・B・テイラー教授(スタンフォード大学)は、講演冒頭において、2008年の国際コンファランスにて自身が行った第1回前川講演(金融研究所発足時の前川春雄総裁の名を冠したスピーチ)の内容を振り返った後、近年の米国をはじめとする各国のインフレと金融政策について論じました。
具体的には、米国をはじめとする各国では、テイラー・ルールが示唆する政策金利と比べて、今回の利上げのタイミングは遅く、低金利期間が長かったことを指摘し、この結果、中央銀行はビハインド・ザ・カーブ(behind the curve)に陥り、高インフレを招いたとの見方を示しました。さらに、この現象は世界的な現象であり、インフレは世界的な問題になった、と述べました。
テイラー教授は、「世界は高インフレ期(a new era of high inflation)に突入したのか」との問いを投げかけ、中央銀行が政策を調整し続けないならば、答えは明確な「イエス」であると指摘しました。中央銀行はこれまで以上にルール・ベースの政策運営を行うことで、ビハインド・ザ・カーブを避けることができ、結果として、経済に大きなダメージを与え得る急速な利上げを回避できると主張し、前川講演を終えました。
【次ページ】基調講演①
前のページへ
3. 基調講演①
内田眞一副総裁(日本銀行)は、現在の日本の物価を巡る動向の変化が、不可逆的なデフレからの構造変化を意味するのか、あるいは、単に一時的な現象にすぎないのか、との論点を提示し議論を展開しました。
最初に、デフレが生じた背景として「成長トレンドの低下」と「慢性的な需要不足」の2つを指摘し、潜在成長率が下がり、自然利子率が趨勢的に低下してきたと述べました。次に、2000年代にかけて、ゼロ金利制約に直面するもとで、日本銀行の金融政策は、実績インフレ率や予想インフレ率を押し上げる十分な力を発揮できなかったと述べました。さらに、社会のコンセンサスとして「雇用を守る」ことが重視され、雇用や企業数の過剰が残された結果、「現在の物価と賃金は将来も変わらない」という、ある種の社会的なノルム(social norm)を生み出し、このノルムが、あたかも、インフレ予想がゼロ%でアンカーされているかのように働いたと指摘しました。
次に、日本銀行は、2013年以降、量的・質的金融緩和(QQE)やイールドカーブ・コントロール(YCC)等の政策によって経済に高圧をかけ続け、政府の諸施策と相俟って、デフレのそもそもの原因である需要不足とその結果として生じた過剰な労働供給は解消された、と述べました。デフレ的なノルムの克服については、答えはそこまで明白ではないものの、近年の世界的なインフレが最後の一押しとして作用し、人手不足が続くもとで、社会的なノルムは解消に向かっていると述べました。
最後に、インフレ予想を2%にアンカーしていくという課題は残っているものの、デフレとゼロ金利制約との闘いの終焉は視野に入っていると評価し、基調講演を締めくくりました。
【次ページ】基調講演②
前のページへ
4. 基調講演②
マーカス・ブルネルマイヤー教授(プリンストン大学、金融研究所海外顧問)は、実体経済が落ち込んだ後に元の状態に戻る力(レジリエンス)について紹介し、レジリエンスを重視する伝統的・非伝統的金融政策の運営について議論しました。
最初に、概念的に、レジリエンスを重視する政策アプローチのもとでは、リスクが顕在化すると実体経済は落ち込むものの、その後、元の状態に戻るため、リスクが顕在化した際のダメージを最小化しようとするロバストネス・アプローチと比べて、実体経済は長期的に高い成長を達成できると論じました。この点、米国のGDPを例に、金融危機は、レジリエンスを損なう「罠(trap)」であると述べました。
次に、金融政策に焦点を当てて、フォワード・ガイダンスは、コミットメントが弱いと効果が限定される一方、コミットメントが強すぎると外的環境変化に適応できずレジリエンスが損なわれ、罠にはまり得るという意味において、トレードオフの関係にあると論じました。また、中央銀行が、赤字や債務超過に陥ると、その受け止められ方次第では信任の低下という罠に陥る可能性があるため、法定準備預金と超過準備の配分見直しを通じて、金融機関への利払いを抑えることも一案であると述べました。さらに、QEを取り上げ、利上げ準備のためのQEを提唱しました。金融機関が大きな金利リスクを抱えるもとでの利上げは金融安定を損なう可能性があるとして、QEによって事前に金利リスクを吸収できれば、利上げの自由度を確保でき、レジリエンスを高められると論じました。
【次ページ】論文報告セッション
前のページへ
5. 論文報告セッション
論文報告セッションでは、物価変動ダイナミクスや伝統的・非伝統的金融政策に関する理論的・実証的な研究が計4本報告され、討論者とフロア参加者も交えて議論が繰り広げられました。
【次ページ】政策パネル討論
前のページへ
6. 政策パネル討論

今回のコンファランスのテーマ「物価変動と金融政策の課題 -- 教訓と展望 --」に合わせて、「物価変動」と「伝統的・非伝統的金融政策の効果」をテーマとした2つの政策パネル討論が行われました。
「物価変動」をテーマとしたパネル討論では、アタナシオス・オルファニデス教授(マサチューセッツ工科大学、金融研究所海外顧問)が座長を務め、チャールズ・L・エバンス(前シカゴ連邦準備銀行総裁兼最高経営責任者)、ピエール=オリヴィエ・グランシャ(経済顧問兼調査局長、国際通貨基金)、オッリ・レーン(総裁、フィンランド中央銀行)、エリ・レモロナ Jr.(総裁、フィリピン中央銀行)、ボシティアン・ヴァスレ(総裁、スロベニア銀行)の5名のパネリストが討論を行い、インフレ予想や賃金、エネルギー価格等、物価変動の主要な決定要因について議論を交わしました。






「伝統的・非伝統的金融政策の効果」のパネル討論では、マーカス・ブルネルマイヤー教授が座長を務めたもとで、ミシェル・W・ボウマン(理事、連邦準備制度理事会)、トーマス・J・ジョルダン(総裁、スイス国民銀行)、ロレッタ・J・メスター(総裁兼最高経営責任者、クリーブランド連邦準備銀行)、イザベル・シュナーベル(専務理事、欧州中央銀行)、氷見野良三(副総裁、日本銀行)の5名のパネリストが、様々な非伝統的金融政策の効果や副作用を振り返り、今後の金融政策運営に対する教訓について議論しました。






* 文中の肩書は国際コンファランス時点のものです。